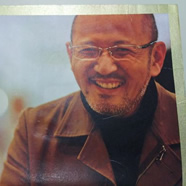第32回国際映画祭のミューズは広瀬アリス
2019年10月28日から11月5日まで開催された第32回東京国際映画祭が閉幕した。今回は、TOHOシネマズ六本木とEXシアターのP&I上映11本を観ることができた。
毎回、世界の作品に触れることで世界を疑似体験し、歴史から学び、今を生きるヒントをもらう事ができるこの機会に感謝している。

©2019「i-新聞記者ドキュメント-」製作委員会
さて今回初めて経験したのが、上映後の会場からの拍手。何年も取材しているが、マスコミ向けのP&I上映で拍手が起こったのは、初めての事だったから少々面食らった。何せクールに観る人たちばかりなのだから。その作品は『i―新聞記者ドキュメント―』で、11月15日から新宿ピカデリー、ユーロスペースほかで公開される。今年ヒット作となった『新聞記者』のリアルドキュメント版で、モデルとなった「東京新聞」の望月衣塑子記者を追いかけたものだ。社会部の記者でありながら、官邸記者会見に出席し、政府側司会者からの発言妨害を受けながらも果敢に挑戦する女性記者の日常の取材活動に密着した力作だ。森友学園問題では、籠池夫妻に独占取材したり、辺野古埋め立て問題の現地取材などでも徹底して疑問をぶつける彼女のスタンスは、ジャーナリストとして当然至極のことなのだが、メディア全体が忖度と同調圧力に屈している今日の危機的状況を分かりやすく詳らかにしてくれる。そしてなんと日本映画スプラッシュ作品賞を受賞したのだ。審査員たちの矜持に敬意を表したい。

© 「海辺の映画館―キネマの玉手箱」製作委員会/PSC 2020
さらに映画の在り方は、軍靴の足音が聞こえてきそうなこのご時勢に警鐘を鳴らす機能を強めているようだ。今回の映画祭で特集された大林宣彦監督の最新作『海辺の映画館―キネマの玉手箱』は、今夜限りで閉館する映画館で戦争をテーマにした上映作品の中へタイムリープする3人の若者という設定で、時にはコメディーのように、時にはCGとアニメのコラージュのように、そして時にはファンタジックな寓話のように展開していく。戊辰戦争、中国大陸への侵略、沖縄戦、広島原爆投下と戦の惨めさ、愚かさ、人々の切なさを訴える。2020年4月公開予定だ。

©Teresalsasi
スペイン・アルゼンチン映画『戦争のさなかで』は、ナチスドイツの後押しを得て政権獲得したフランコが台頭する時代に生きた哲学者で劇作家のミゲル・デ・ウナムーノを描いた作品。ファシズムを甘く見ていたことに気づき、自身が学長を務めていた内戦下のサラマンカ大学で、反乱軍(フランコ軍)兵士を前にスペイン人すべての平和を願った反戦演説を行い、学長を更迭されるまでを描く。だんまりを決め込むこともできた環境だったが、壇上で耐えられず、演説を始めるウナムーノの哲学者としての信念が、観る者に鋭く問いかけてくる。

『戦場を探す旅』はフランス・コロンビア合作で、1860年代、当時は黎明期だった報道カメラマンがメキシコ干渉戦争中のフランス軍の写真を撮りに行く道程の話だ。フランス軍将軍の許可を受けた報道カメラマンがジャングルを戦場探しに歩く。現地のメキシコ先住民と出会い、彼を弟子に連れ歩きながら戦場へとたどり着く。弟子との友情も生まれ、いざ戦場の写真を撮れるかと思いきや。実はクリミア戦争で息子を失った事を心に仕舞い込んでおり、息子の惨状の追体験が目的だったのかもしれない。
「正義」のもとに「正義」の存在しない戦争を繰り返す人類の目を覚ますことは、いつになったらできるか。

©Authrulu (Shanghai) Digital Media Co.,ltd.©Youth Film Studio
続いてテーマに挙げられるのは都会と田舎、閉ざされた社会や因習とその外の世界といった環境の対極性。
中国映画の『チャクトゥとサルラ』は、内モンゴルに住む夫婦の関係性を閉じた社会と開けた社会の対比で描いている。夫のチャクラは、大草原での慎ましい暮らしに飽き飽きして、都会へと出たがり、妻のサルラは自然や動物と共に生きる毎日を大切に思う。互いに必要としていながら、すれ違う二人の日々を美しい草原の景色と都会化が進む街を交えながら描き、最優秀芸術貢献賞を獲得した。

©BNK48 FILMS
タイの『私たちの居場所』は、BNK48のメンバーが数人登場する青春映画。ジェニスが演じるスーはフィンランドへの留学を目指すが、本音は今の暮らしから逃れたいだけのよう。ミュージックが演じる親友のベルは、そんなスーを支えるが、自身はこの田舎町から出ようとは考えていない。二人が抱える家族や亡くなった母親への想いなどが交錯して、タイの田舎町と世界との乖離を感じさせる。

移民問題を絡めて田舎の地域社会の閉塞感を描いたスウェーデン映画『約束の地のかなた』は、ルーマニアから働き口を求めてスウェーデンにやってきた少女サビーナと街の少女エーリンとの間に芽生えた友情を軸に、移民に対する差別感も根強い田舎町の風景の中で、彼女たちの交流と旅立ちを見つめた作品だ。舞台となる街には、汚染物質を川に流す工場があり、時折、飛行機がこの汚染物質を中和させるための薬剤を散布するが、これが雪のように見えて美しくもあり、毒々しくもある。まるで原発施設を補助金で押し付けてきた日本各地の美しき田舎町が重なって見えるようだ。都合の悪いものを田舎に押し付けて、その田舎町は移民を排除したいと頑なに保守化していく。社会全般に通底する課題をさりげなく織り込んで、ピュアな二人の少女の友情だけが明るい未来を指し示しているという事かもしれない。

©Kaz Film
トルコ映画『湖上のリンゴ』は、凍った湖上に落ちている1個の齧りかけのリンゴから始まる。それがどうしてそこにあるかが紐解かれていく。1960年代のアナトリアの田舎町を舞台に母と暮らす少年ムスタファの初恋の話。ムスタファは、アシュク(吟遊詩人)になるため、親方のもとで修業に励む。初恋の少女から赤いリンゴを土産として頼まれる。アシュクの技を披露する会がまるでラップバトルを思わせて面白い。歌いながら、対戦相手を罵倒するのは、実は昔からある作法なのだと発見させられる。さて旅先からリンゴを持ち帰ったムスタファは、少女の婚礼の宴でリンゴを渡し、民族楽器のサズを弾き歌う。親方も歌うのだが、それを遮るように新郎がダンス音楽を命じて、民俗音楽はかき消されてしまう。この辺りに消えゆく伝統と現代化の波の相克が垣間見える。

©Bagnold Films Ltd 2019
『バクノルド家の夏休み』はイギリス映画で、青年と母親の交流を描く。夏休みに離婚した父親が住むフロリダに行く予定だったが、ドタキャンになってガッカリの15歳、ダニエルはヘビメタ好きで、その風貌と態度からアルバイトがなかなか決まらない。図書館勤務の母親はダニエルの学校の歴史教師にデートに誘われる。揺れ動く母と息子の掛け合いが愛おしい作品。ロンドン郊外の長閑な住宅街からフロリダへ行く憧れやヘビメタバンドの未来など、広がる世界への未来を感じさせるハートウォーミングストーリーだった。

©2019「花と雨」製作委員会
『花と雨』は、ラッパーSEEDAのアルバムから着想を得て作られた。主人公の青年を若松将、彼を支える姉役が大西礼芳。そして大麻密売組織の女親分役が紗羅マリーなのだが、彼女はミュージシャンでもあり、ストリートブランド「イロジカケ」のデザイナーでもある。さて本題へ。心の葛藤をラップで歌にぶつける主人公だが、大麻の栽培、売人へと手を染めて転落していく。理想と現実、闇社会と表社会、「板子一枚下は地獄」の不条理を垣間見せ、閉ざされた世界とその外界の狭間でもがく青年群像も都会化の歪みと矛盾の産物なのだろう。そこに潜む人間の弱さが本作の主要な観点のような気がした。2020年1月17日からヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開予定。
東京国際映画祭を通じた映画を巡る旅は、インナートリップでもあり、世界を疑似体験する貴重なツールでもあると、つくづく思った1週間だった。